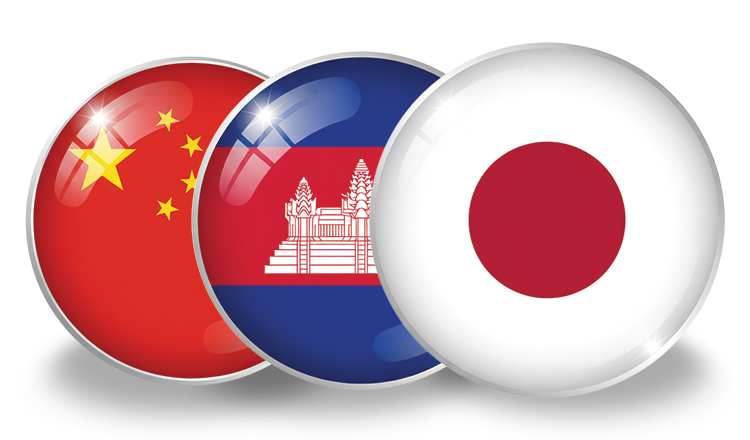中国と日本の間で台湾問題をめぐる外交的緊張が再び高まる中、東アジアの安全保障環境の脆弱性が改めて浮き彫りになっている。北京が長年の立場を改めて強調し、東京が台湾問題により直接的に関与する姿勢を示す中、地域諸国はアジアの二大影響力国家の対立激化というリスクに直面している。中国と日本の双方と緊密な戦略・開発パートナーシップを維持してきたカンボジアにとって、これらの緊張は決して遠い問題ではない。地域の安定、経済的つながり、そしてアジアの長期的な成長への影響を現実的にもたらす可能性がある。しかし、北京と東京の間で言葉が鋭さを増しているにもかかわらず、カンボジアの立場は一貫している。すなわち、中立の堅持、平和的対話の支持、そして国際的に認められた外交枠組み――特に「一つの中国」政策の尊重である。カンボジアは台湾問題を、中国がいかなる状況下でも譲歩できない(レッドライン)として認識している。
カンボジアの立場は明確である。プノンペンは長年、一つの中国原則を中国との外交関係の基礎としてきた。これは政治的な利便性のためではなく、より広範な外交理念――内政不干渉、主権尊重、外部勢力による国内問題への介入反対――の表れである。干渉と地政学的対立に揺さぶられてきた歴史経験は、これらの原則を重んじる姿勢を強化してきた。
同時に、カンボジアは中国と日本の双方を、最も信頼できる建設的パートナーとして高く評価している。両国は、カンボジアの紛争後復興、経済発展、制度構築において重要な役割を果たしてきた。中国は大規模インフラ投資と経済協力を、日本は統治、教育、人材育成に長年貢献してきた。これらの関係は長期的で相互補完的であり、不可欠なものとカンボジアは捉えている。
また、中国と日本はカンボジアとタイの国境問題を含む地域紛争において、対話・協議・平和的解決を一貫して支持してきた。軍事的対立への拡大を断固として回避するよう促してきたこうした建設的外交姿勢は、現在の緊張を一層懸念すべきものとしている。これこそが、両国に自制と平和的解決への復帰を求めるカンボジアの声をより強めている。
カンボジアが中国・日本間の緊張を強く懸念するのは、双方が東アジアのサプライチェーン、イノベーション、生産・金融ネットワークの中核を担っているためである。特に台湾海峡危機を契機として両国関係が悪化すれば、東南アジアを含む地域経済に甚大な影響を及ぼす可能性がある。
地域の貿易ネットワーク、投資、観光に大きく依存するカンボジアにとって、東アジアの安定は周縁的問題ではなく、国家発展の核心に位置づけられる。
したがってカンボジアは、中国と日本の双方に対し、自制と対話再開を強く訴えている。戦略的認識には違いがあっても、平和と経済的相互依存、海上貿易の安定という共通利益は大きい。これらの利益こそが、誤算による対立を回避するための指針となるべきだ。
カンボジア外交の中心にあるのは「中立」である。他の中堅国が採る「曖昧な均衡外交」とは異なり、カンボジアの中立は明確かつ直接的である。すなわち、どちらの側にも偏らず、すべてのパートナーと建設的関係を維持しつつ、いかなる大国間対立にも巻き込まれない姿勢である。これはASEANの長年の原則――コンセンサス、不対立、主権尊重――とも整合的だ。
さらにカンボジアは、ASEAN自身が安定化の役割を果たすべきだと考えている。東アジアサミットやARFなど、主要国を一堂に会する枠組みを有するASEANは、緊張が高まる中でも対話の場を提供できる。カンボジアは、ASEANが戦略的不信の緩和に努め、中国・日本を含む外部パートナーとの対話促進に寄与することを支持する。
カンボジアのメッセージは明快かつ現実的である。「平和はすべての国に利益をもたらし、衝突はアジアの数十年にわたる経済的進歩を損なう」ということである。カンボジア自身もタイとの国境問題において、停戦と和平合意の完全な順守を改めてタイに求めている。サプライチェーン再編や貿易政策の急変など、世界の不確実性が高まる中、アジアは台湾海峡の緊張や中日関係の深刻化に耐えられる余裕はない。
プノンペンは、中国と日本が引き続き外交を優先し、戦略的な相違を責任ある形で管理し、予期せぬ衝突リスクを高める行動を避けることを期待している。両国がカンボジア・タイ国境問題の際に示した、対話・協議・平和的手段による建設的外交は、両者自身の問題を管理するうえでも有効なモデルとなり得る。カンボジアは、地域の安定、信頼醸成、平和共存を促進する取り組みを支える用意がある。
複雑化する地政学情勢の中で、カンボジアの姿勢は経験と原則に基づいている。一つの中国政策の堅持、中国・日本との友好関係の維持、そして平和と発展を守るための中立の立場である。さらに重要なのは、中国も日本もどちらか一方を選ぶよう各国に圧力をかけたことがないという点だ。小国であっても、対立の世界で意味ある役割を果たせる――側に付くのではなく、対話・安定・協力を一貫して訴えることでそれは可能である。